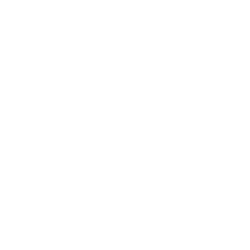- 2025年11月 5日
- [その他]
- 国・地域:日本
- トピック:ビジネスと人権
ビジネスと人権に関する行動計画(NAP)とは、企業による人権への負の影響に対して、国連のビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)に即して人権が守られるよう、国が策定する政策文書のことです。日本政府は2025年10月、この計画の改訂版原案に対するパブリックコメントによる意見募集を行い、アムネスティ日本として下記の意見を提出しました。
アムネスティ日本が提出した意見全文
<全体に対する意見>
【意見内容①】
本行動計画原案についての意見募集を日本語に限定すべきではない。また、行動計画は、最低でも英語版を日本語と同時期に公表すべきである。
理由:日本企業や政府が関わる事業活動のステークホルダーは国内外に存在しているため、日本語に加えて主要な他言語、少なくとも英語での対応を可能にし、幅広いステークホルダーの参加を促すべきである。
特に、「第2章 優先分野」「2『誰一人取り残さない』ための施策推進」には、「(2)外国人労働者」が含まれている。日本語話者でないライツホルダー(権利保持者)に対する施策が行動計画に含まれるのであれば、行動計画原案が日本語だとしても、日本語以外での意見提出を受け付けるべきである。
【意見内容②】
旧計画においては、理念的な内容も含まれていたが、本計画案においては、それらが捨象されている。今回においてもそれらは捨象せず、記載すべきである。旧計画にあるコロナ・オリンピックなどの記載内容のような今回には合わない箇所を改定し記載を続けるべきである。
理由:世界人権宣言や国際人権規約など世界の趨勢は人権の確保・拡大の方向へ向かっている。本計画案ではこれらの人権の確保・拡大の理念が省略されており、代わって「国際競争力の確保P8」、「諸外国の法制度への対応P8」、「日本企業が不利な立場に置かれることがないようP8」、「グローバルな投資家からの評価P9」など、行動計画が、企業にとって有利になるからとの記述が目立つ。行動計画が企業にとって有利に働くことは、副次的効果として記載することは許容できるが、主要目的ではない。主要目的として記載すべきことと副次的に記載することが逆転している。これでは行動計画が「企業にとって有利に働く」範囲に限定されてしまうおそれがある。
【意見内容③】
「自由権規約の個人通報選択議定書」を批准すべきである。批准にあたっての課題については、課題解決のための検討を継続する旨を本計画に明示すべきである。
理由:日本は1979年に国際人権規約を批准したが、「自由権規約の個人通報選択議定書」は批准していない。国内での人権保護や海外でビジネス等に携わる人びとの保護のため、速やかに議定書を批准すべきである。
<第1章:行動計画が改定されるまで (背景及び作業プロセス)>
3 行動計画の改定及び実施を通じて目指すもの
【意見内容①】
企業の事業活動によって影響を受ける人びとの人権を保護する義務は、国にあることを明記し、国としてライツホルダーの人権保護を第一に考えているという姿勢や、国が積極的に企業や政府機関に要請し、人権保護を徹底していくという姿勢を明確に示すべきである。具体的には、人権デュー・ディリジェンスの法制化、国家が所有または支配する企業におけるの人権デュー・ディリジェンスの確保や、公共調達における取引企業の人権尊重を促進するべきである。
理由:本行動計画の策定においては、人権保護の義務は国にあるという認識を明確に示し、指導原則の根本にある国の義務が軽んじられることがないようにすべきである。
【意見内容②】
2023年に改定された「開発協力大綱」にも言及し、基本的人権の保障を掲げる本大綱に基づいて実施されるODA事業が新たな行動計画と一貫性を持って推進されることを示すべきである。
理由: 行動計画の実施を通じて、ODA事業に関わる政府機関の人権保護義務や日本企業の人権尊重責任が果たされるよう、「開発協力大綱」と行動計画の一貫性を示すべきである。
【意見内容③】
政府は、企業による人権デュー・ディリジェンスや情報開示の義務化の検討を早期に開始すべきである。法制では、違反企業に対する罰則や公共調達の入札手続きからの除外措置を設け、企業による人権侵害の被害者に対しては、民事上の損害賠償責任を確保するべきである。
理由: 一定の規模の事業所、あるいは、一定の業種の企業に対して、人権デュー・ディリジェンス、または、その実施についての情報開示を義務化する法規制が欧米を中心に進み、アジア地域でも、韓国、タイ等で人権デュー・ディリジェンス法案の検討が進んでいる。日本でも、企業の義務としての人権デュー・ディリジェンスや情報開示の法制化を検討すべきである。
【意見内容④】
日本企業が国境を越えて引き起こす、または、助長する人権侵害についての責任や、日本企業の国内外の子会社による人権侵害についての親会社の責任を追及できる人権デュー・ディリジェンスの法制化を検討すべきである。
理由: 人権条約上、国は自国の領域および管轄権の外にいる人びとの権利をも保護する義務がある。日本の法的管轄外の場所で起きた人権侵害や、子会社による国外での人権侵害など、負の影響を受ける人びとが救済措置へアクセスすることが困難なケースについても、ライツホルダーの人権保護が可能となるような施策を国は取るべきである。子会社を含む企業グループとそのサプライチェーンを対象とした人権デュー・ディリジェンス法制を検討するべきである。
4 行動計画の改定プロセス
【意見内容】
行動計画の改定毎に、ギャップ分析を行うべきである。
理由:行動計画の策定において、目標、課題、行動プロセスを設定するには、ギャップ分析が有効であるため。また、国連人権理事会の報告(A/HRC/56/55/Add.1)においてもギャップ分析を含めるべきとの勧告が行われている。
なお、ギャップ分析のプロセスにおいては、国連の諸機関による勧告に加え、NCPの活用も考慮すべきである。
<第2章 優先分野>
全体
【意見内容①】
「第2章 優先分野」にステークホルダーとの対話(コミュニケーション)機会の増強を含めるべきである。
理由:「誰一人取り残さない」という観点から、課題となる人権セグメントに属する人びととの対話が欠かせないため。
ステークホルダーとの対話体制を強化するため、課題となる人権セグメント毎に、旧計画における「連絡会議」の下部組織として、ステークホルダーとの対話の実施、課題、行動プロセス案を策定する組織を設けることが重要である。
【意見内容②】
「取組の方向性及び具体的施策の例」に記載される 内容として、主管府省庁・施策内容・実施時期を示すとともに、ライツホルダーが受けている人権への負の影響の防止・軽減、是正・救済につながる、実施内容の実効性を測るための指標等を示すべきである。
理由:本計画案が「行動計画」であるならば、計画内容である行動について、どの府省庁がいつまでに何を実行するのかがわかるように具体的に示し、すべてのステークホルダーが計画の実行主体および実施内容を把握できるようにし、実施時期や実施状況を確認できるようにすべきである。
「8 実施・モニタリング体制の整備」とも重なるところではあるが、行動計画を主管する外務省が全府省庁の動きを把握してモニタリングすることは難しいため、各府省庁の施策・実施時期・実施状況・モニタリングのための指標を明確にすることで、関連ステークホルダーがモニタリングすることが可能となる。
1 人権デュー・ディリジェンス及びサプライチェーン
【意見内容①】
人権デュー・ディリジェンスの実施および情報開示について、国が企業に求める対応の具体的な内容を示した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」に沿った企業の対応の現状を把握し、ライツホルダーや関連ステークホルダーが指摘する企業が抱える課題とその解決のために必要な支援を明示するべきである。
理由:「(1)課題認識及びこれまでの取組」で示されているのは、企業の人権リスクと影響を受けるライツホルダーであり、なぜそうしたリスクと影響が防止・軽減できないのかというところが説明されていない。そのため、「(2)取組の方向性及び具体的施策の例」にあげられている施策がライツホルダーの受けている人権への負の影響に対処するものとはなっていない。ガイドラインに沿った対応を進める企業が増えている中で、ライツホルダーへの影響の防止・軽減、是正・救済につながっているのか、つながっていなのであれば、何が課題となっているのかを把握し、政府としてどういった支援が考えられるのかを示すべきである。
【意見内容②】
過労死・過労自殺撲滅の目標を示すべきである。
理由:過労死等の労災認定は2024年度1,304件で過去最多、過労に関連する自殺・自殺未遂は89件、精神障害は1,000件を越えている。人間の生死は最大の人権問題である。
【意見内容③】
労働災害により4日以上休業する労働者について、少なくとも2009年レベルよりも、さらに少なくすることを目標に掲げ、行動計画に示すべきである。
理由:労働災害により4日以上休業する労働者は2009年を底に増加傾向にあり、2024年は過去20年間で最多といわれている。労働者の安全衛生への配慮は「ビジネスと人権」を語るうえで、重要な要素である。12ページに「安全衛生」の言葉はあるが、これをより強調し、安全衛生への配慮を徹底し、ITその他の技術についても活用しながら、労働災害の減少に努めるべきである。
2 「誰一人取り残さない」ための施策推進
● 全体
【意見内容①】
職場での差別やハラスメント防止のため、性的指向・性自認や表現による差別、人種差別、民族・国籍差別、歴史的差別をはじめとするあらゆる差別を対象とする包括的な差別禁止のための法的な措置に関する記述を含めるべきである。
理由:2020年の国連自由権規約委員会第130会期日本審査に際する日本政府への勧告にも記されているとおり、包括的な差別禁止法の導入あるいは他の法律の組み合せにより、性的指向、性自認、表現、ならびに民族や国籍などすべての理由に基づく差別からすべての人を平等に保護することに関する記述を求める。
【意見内容②】
「第2章 優先分野」「2『誰一人取り残さない』ための施策推進」に非正規労働者を加えるべきである。
理由:相対的貧困の要因の一つと考えられる非正規労働者の正規雇用へ転換していくことが、不安定な経済的・社会的立場にある非正規労働者の人権の向上につながるため。
【意見内容③】
選択的夫婦別姓を推進するべく、原案にある「更なる検討の実施」にとどめず「実現に向けた実施作を検討」するべきである。推進にあたっての課題については、早急に課題解決のための具体策を検討をする旨を本計画に明示すべきである。
理由:経団連からの提言もあり、男女雇用機会均等法・男女共同参画社会基本法の主旨や男女ともに労働する社会において、姓の変更を強いることは、個人のキャリア形成、海外での研究・業務への障害になる。
(2)外国人労働者
【意見内容】
「第2章 優先分野」「2『誰一人取り残さない』ための施策推進」の「外国人労働者」は、「外国人移住者」と言った外国人材の家族を含めるべきである。また、施策内容についても外国人材とその家族を含む移住者との「共生」を優先事項としたものにすべきである。
理由:旧計画において「外国人材の受け入れ・共生」として、「共生」を掲げていたが、本計画案においては、外国人材に帯同する家族、および「共生」に関する施策に関わる部分が非常に弱くなっている。
「共生」は外国人移住者の人権課題を解決するための一つの重要な目標である。
3 テーマ別人権課題
●(1)AI・テクノロジーと人権
【意見内容①】
違法な監視から保護される権利をすべての人に対して国が保障するべきである。そのための措置を「具体的な措置」に含めることを求める。特に日本では個人情報保護法などで保護されるとしか規定されていないプライバシーの権利を、憲法第13条の実体的権利の一つとして明示した法制度が必要である。
理由:2017 年 11 月のUPRに際する日本政府への勧告に記したとおり、監視や個人情報の収集を可能とする技術が、プライバシーの権利等の侵害や治安維持等を理由とした不当な監視や情報収集につながらないよう、ライツホルダーの保護の観点から適切な対策を行うべきである。日本では、プライバシーの権利は、行政による保護の対象でしかなく、データ主体自身による救済手続きが訴訟に訴えない限り行えない。個人であるデータ主体への救済策が圧倒的に足りないままである。特定個人情報についても、救済策は実際的にはほとんど個人に対しては権利として開かれていない。これは、当然のことながら欧州基準にも合致していない。
【意見内容②】
人工知能(AI)の機械学習などの新しい技術の使用による人権侵害からの保護についての対策を「具体的な措置」に含めるべきである。
理由:新技術による利便性の向上と同時に、差別の助長といった問題が指摘されており、プライバシーの権利、表現の自由の権利、文化的生活に参加する権利、法の下の平等、個人情報保護などの侵害のおそれが懸念される。国や企業が新技術を使用する際には、人権への影響を評価して、負の影響を予防し、または軽減するための措置を義務付けるとともに、人権侵害がおきた場合の救済へのアクセスを「具体的な措置」として保障するべきである。
生成AIの利用について、データの収集に際して差別を助長する可能性があることはすでに各所から指摘されている。この点については人種差別撤廃条約でも懸念されているものであり、条約機関の最近の一般的勧告でも特に指摘されているところである。国際人権基準に沿う形で、AI利用についての具体的な指針を打ち出すべきである。
【意見内容③】
技術的なことが主となる裁判においては裁判の制度のなかで第三者技術委員会を設置し、検察官・被告人(もしくは原告・被告)のどちらかの希望により、同委員会の開催を要請することができるようにするべきである。また、裁判官はその委員会の答申に対して尊重しなければならないこととするよう働きかけるべきである。
理由:大川原化工機事件の反省を踏まえ、技術的な事柄について裁判制度のなかで正しく検証できるようにしていくため。
6 公共調達・補助金事業等を含む公契約
【意見内容】
公共調達における取引の条件として、人権デュー・ディリジェンスの適切な実施とそれについての情報開示を求めることを「具体的な措置」に含めるべきである。また、政府は入札企業が人権デュー・ディリジェンスの実施を通じて人権尊重を確保していることを確認した経緯や理由等を公表し、手続きの透明性を確保するべきである。
理由:公共調達における取引では、取引先の企業で働く労働者の人権状況や、取引対象の製品・サービスのサプライチェーンの人権デュー・ディリジェンスの実施状況の確認を、国から企業に要請するだけでなく、国が自ら行うべきである。2023年4月にはビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定「公共調達における人権配慮について」が公表されているが、政府が具体的にどのように人権尊重を確保しているかに関する情報は公表されていない。
7 救済へのアクセス
【意見内容】
非司法的救済措置として、国内人権機関の設置に向けた行動を「具体的な措置」に含めるべきである。合わせて、他の行政から独立した人権監視メカニズムの設置を急ぐべきである。
理由:「OECD多国籍企業行動指針」に基づく日本NCPは、実効性に欠け、ライツホルダーの保護の観点からは十分に機能しているとは言えない。2017 年 11 月のUPRに際する日本政府への勧告に記しているとおり、パリ原則に即した国内人権機関の設置に向けて国が直ちに行動することを求める。
行政から独立した国内人権機関の設置については、会計検査院や人事院にみられるような行政に対する監査機能を持つ機関として明確に行政からの独立とその構成の多元性をうたうべきである。
併せて、OECDのNCPについても現状の3省による行政連絡機構としてではなく、実際に措置を講じることができる独立機関として設置し、他国のNCPと連携した国際的な措置が実行可能な機関として定立するべきである。またNCPの任務に対しては、行政から独立した国内人権機関による監督が実効的に行える関係性を持つべきである。
こうしたNCPに対する苦情申し立て(グリーバンス)手続きや、拷問等禁止条約選択議定書が定め、刑事施設被収容者処遇法上の不服申し立て手続きが予定する「拷問防止メカニズム(NPM)」を実効的に運用するためにも、救済へのアクセスの制度的担保については、可及的速やかに措置を講じるべきである。また、そうした苦情や不服について、データベースに集積し、必要に応じて参照できる体制を構築することも、指導原則の3本目の柱であるremedyが求める根本的な要請である。
<第4章 今後の行動計画の実施および見直しに関する枠組み>
【意見内容】
行動計画の進捗について、第三者によるモニタリングを実施すべきである。また、各施策の実施状況の評価にあたっては、各施策のステークホルダーが参画あるいは関与すべきである。
理由:行動計画の実効性を担保するには、第三者機関によるモニタリングにより、計画の進捗を客観的に確認することが重要である。
また、各施策の実施および進捗状況の評価にあたっては、各施策のステークホルダーの一角であるライツホルダーの関与は評価の適正性を向上させる可能性が高い。
以上
関連ニュースリリース
- 2025年12月16日 [公開書簡]
日本:生命の危機にあるムスタファ・カリルさんの強制送還を直ちに停止せよ - 2025年11月28日 [国際事務局発表ニュース]
日本:同性婚訴訟 東京高裁判決は平等への道を逆行 - 2025年9月30日 [日本支部声明]
日本:ウィシュマさんの動画開示請求に対し国際人権法の遵守を強く求める - 2025年7月25日 [公開書簡]
日本:「入管ゼロプラン」に反対し、外国人を排除しない、国際人権法に基づく共生のための制度改革を求める - 2025年7月16日 [NGO共同声明]
日本:参議院選挙にあたり排外主義の煽動に反対する NGO緊急共同声明