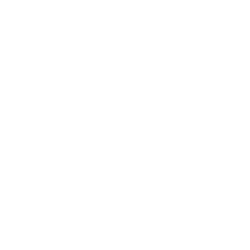創価学会大阪女性平和委員会による若い世代を対象とした講演会で『私たちの声が重なるとき、社会はやさしく動きはじめるージェンダーの視点が切り開く、わたしたちの未来ー』と題しアムネスティ大阪事務所の職員が講師を務めました。冒頭、アムネスティ・インターナショナルがロンドンで設立された経緯、現在200以上の国と地域で展開されているアムネスティの活動が紹介され、NGO誕生のきっかけは、特に若い参加者の関心を集めたようです。
参加者には高校生や大学生世代の姿が多く、会場にはカップルや家族で参加している人たちも含め200名が熱心に耳を傾けます。冒頭「ジェンダーという言葉を知っていますか?」という問いかけには多くの手が挙がりましたが、「その意味を自分の言葉で説明できますか?」という質問には数人のみ。講義では、SEX(生物学的性差)とジェンダー(社会的・文化的性差)の違いや、ジェンダーという概念が生まれた背景を解説。日本におけるジェンダー格差について、小学校での経験を振り返りながら「これもジェンダーの問題かもしれない」と語り合う時間も設けられ、会場はにぎやかに議論が交わされました。
ジェンダー格差のない学校生活の議論をもとに、ジェンダー格差がない社会について以下のようにまとめていきます。
- 性別に基づく役割分担や期待が固定化されることなく、個人の意思と能力が尊重されること
- 教育、雇用、政治をはじめとするあらゆる分野において、性別にかかわらず平等な機会が保障されていること
- 法制度および社会的仕組みが、性別に起因する差別や不利益を未然に防止し、是正する機能を有していること
- 性の多様性が社会的に認知・尊重され、すべての人が安心して自己のあり方を表現できる環境が整備されていること
また、ジェンダー格差の解消は、女性の問題だけではなく、少数民族、障がい者、子ども、外国にルーツを持つ人々など、他のマイノリティの課題とも深く関わっていること、そして複合差別や交差性差別の視点にも踏み込み、人権の視点から説明がされました。
終盤では、アイスランドで約50年前に実施された「女性の休日」、2024年欧州人権裁判所で、シニア女性たちが起こした気候変動対策に関する訴訟の原告側を支持する歴史的な判決、また、岐阜県黒川村の満蒙開拓団の終戦直後の事実と女性の尊厳を回復する過程について紹介がありました。女性同士の連帯や、異なる立場から支援する「アライ」の存在が社会変革を促した事例としてあげられ「こうした動きが広がることを願う」といった声が参加者から多く寄せられたことも印象的でした。
講演後には、高校生を中心とした意見交換の場が設けられ、ジェンダー格差の実感や、是正に向けた悩み・提案が活発に交わされました。
| 実施日 | 2025年11月1日 |
| 場所 | 関西池田記念会館 |